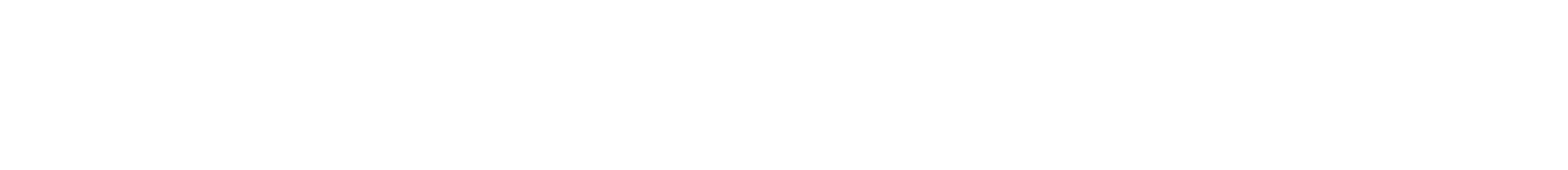年末のご挨拶

ドキュランドへようこそ。「衛生兵キューバとアラスカ ウクライナ・夢も人生も諦めない」を見て
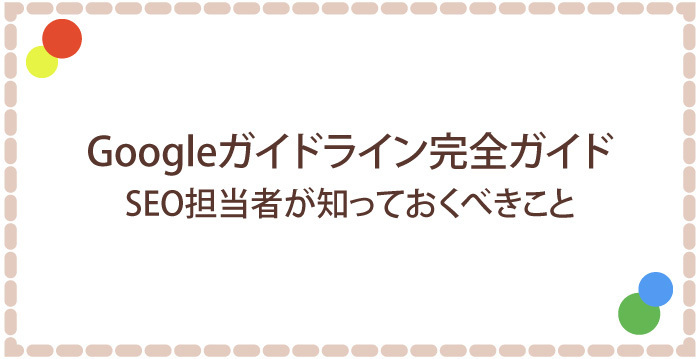
Googleガイドライン完全ガイド:SEO担当者が知っておくべきこと
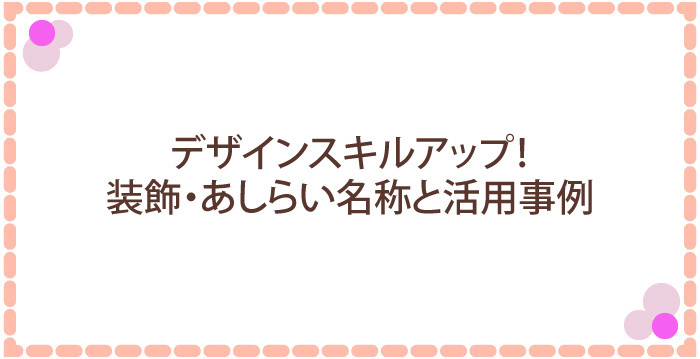
デザインスキルアップ!装飾・あしらい名称と活用事例
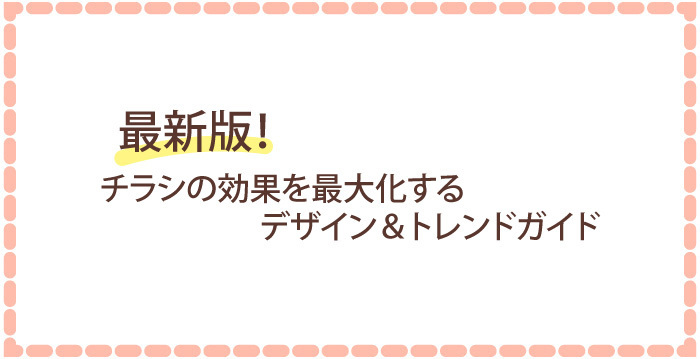
最新版!チラシの効果を最大化するデザイン&トレンド完全ガイド
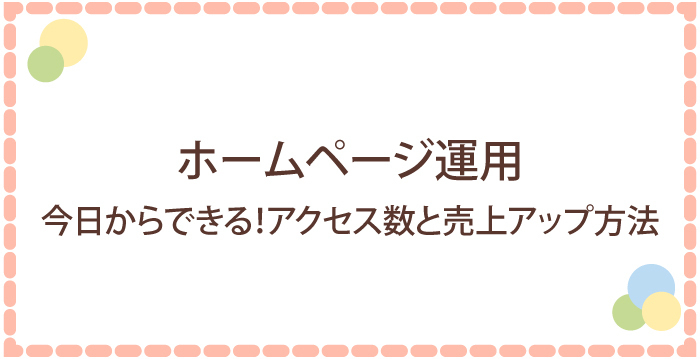
ホームページ運用:今日からできる!アクセス数と売上が劇的に変わる方法
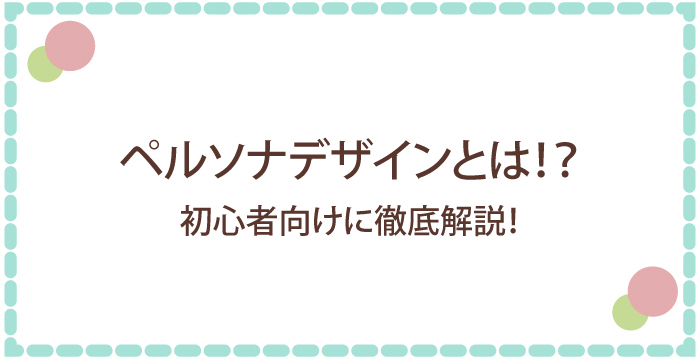
ペルソナデザインとは?初心者向けに徹底解説!作り方から活用事例まで
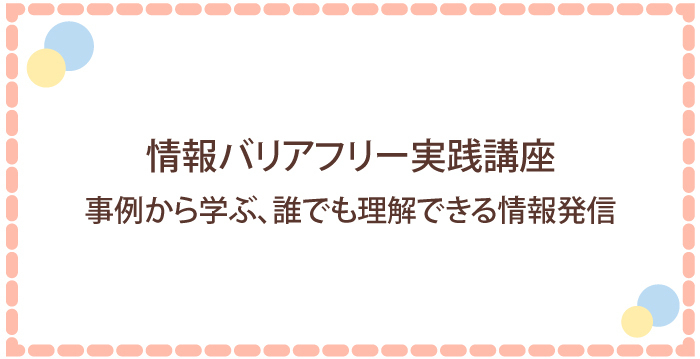
情報バリアフリー実践講座:事例から学ぶ、誰でも理解できる情報発信
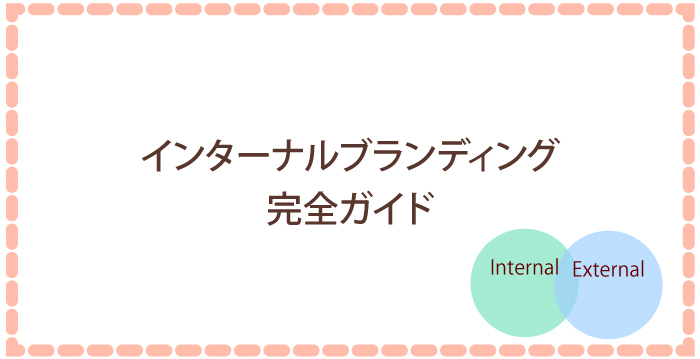
【決定版】インターナルブランディング完全ガイド
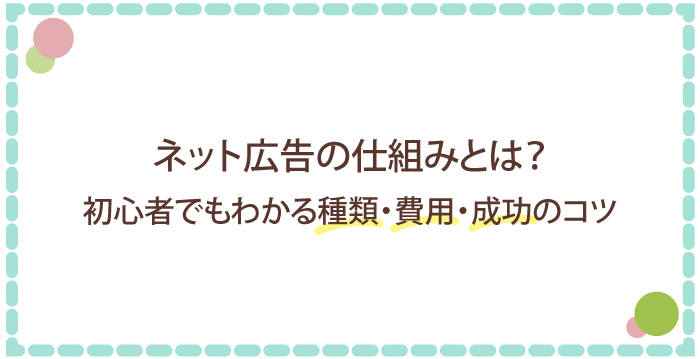
ネット広告の仕組みを分かりやすく解説!初心者でもわかる種類と費用、成功のコツ

リマーケティング広告とは?初心者向け完全ガイド:設定方法から効果測定まで
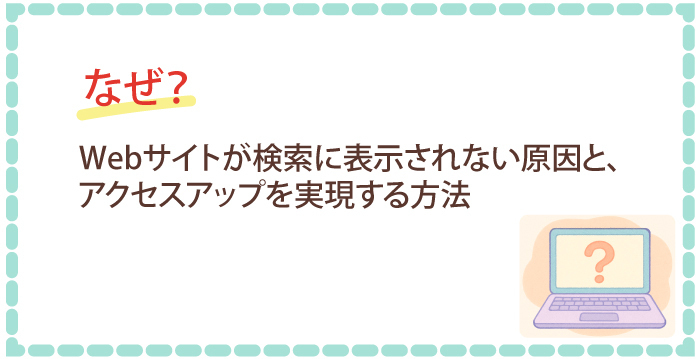
なぜ?Webサイトが検索に表示されない原因を特定し、アクセスアップを実現する方法