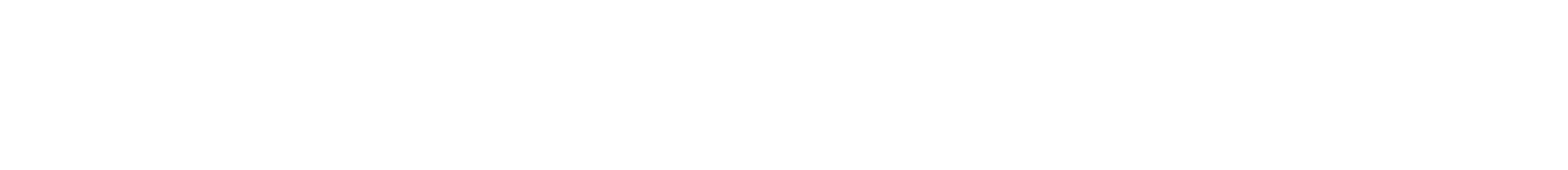2025/10/16

新規でホームページを制作する必要がある、既存のホームページのデザインをリニューアル(=作り直す・刷新する)したいといった背景を持つ読者に対し、デザイン決定の初期段階で考慮すべき重要な要素を解説します。目的の明確化、ターゲット設定、競合分析(=他社サイトの調査)が、後のデザイン制作を成功させるための土台となることを伝えます。ターゲットニーズ(=お客様が求めていること)にある「自社のホームページの目的に合ったデザインを決めたい」という要望に応えるための導入部分となります。
◆目的を明確にする
ホームページ制作やリニューアルにおける最初のステップは、その目的を明確に定義することです。ホームページが達成すべき具体的な目標は何でしょうか?例えば、新規顧客の獲得(=集客)、ブランドイメージの向上(=会社やお店の印象を良くすること)、製品やサービスに関する情報提供、既存顧客へのサポート、採用活動の強化など、目的は多岐にわたります。目的が明確でなければ、デザインの方向性が定まらず、結果として効果の薄いホームページになってしまう可能性があります。どのような成果を期待するのかを具体的に言語化し、それをデザインに反映させるための羅針盤としましょう。
◆ターゲットを定める
次に、誰にホームページを見てほしいのか、ターゲットとなるユーザー層を具体的に設定することが重要です。ターゲットユーザーを「ペルソナ(=理想的な顧客像)」として具体的に定義することで、彼らのニーズ(=必要としていること)、興味、行動パターン、そして抱える課題を深く理解することができます。例えば、「30代の働く女性で、健康的な食生活に関心がある」といった具体的なペルソナを設定することで、どのような情報を提供すべきか、どのようなトーンで語りかけるべきか、どのようなデザインが好まれるのかといった、デザインやコンテンツ制作における意思決定が格段にしやすくなります。ターゲットに響くデザインこそが、ホームページの成功を左右します。
◆競合サイトを分析する
自社のホームページデザインを検討する上で、競合他社のウェブサイトを分析することは非常に有効な手段です。競合サイトを調査することで、業界のデザイントレンド(=流行の傾向)やユーザーが期待するUI/UX(=使いやすさや見やすさの設計)のレベル感を把握できます。また、競合がどのような情報を発信し、どのような強みをアピールしているのかを理解することで、自社サイトとの差別化ポイント(=他社と違う強み)を見つけ出すヒントが得られます。さらに、競合サイトの良い点や参考になる点は積極的に取り入れ、悪い点や改善すべき点は自社サイトで避けるべき教訓として活かすことができます。この分析を通じて、より魅力的で効果的なデザイン戦略(=狙いを持った計画)を構築しましょう。
ウェブサイトのデザインは、単に見た目を美しくするだけでなく、ユーザー体験(=使いやすさや心地よさ)やブランドイメージに大きく影響します。このセクションでは、デザインの専門知識がない方でも理解できるように、ホームページデザインの根幹をなす要素を解説します。色彩心理(=色が人の印象や感情に与える影響)、フォントの選び方、レイアウトの基本原則(=配置のルール)、画像の活用法など、具体的な例を交えながら視覚的に分かりやすく説明し、デザインの「なぜ?」を解消していきます。ここでは、デザインにおいて必須となる「色」「フォント」「レイアウト」「画像」の4つの要素を網羅し、専門用語は適宜解説を加えながら、図解やイラストを多用するイメージで、直感的に理解できるような説明を心がけます。
◆色彩
色は、ウェブサイトの第一印象を決定づけ、ユーザーの感情や行動に直接影響を与える強力なツールです。色彩心理学(=色と感情の関係を研究する学問)では、特定の色が人間の心理にどのような影響を与えるかを研究しており、例えば、暖色系の赤やオレンジは活気や情熱、注意を引く効果があり、寒色系の青や緑は落ち着き、信頼感、安心感を与える傾向があります。ウェブサイトのデザインでは、ブランドイメージや伝えたいメッセージに合わせて、これらの色の特性を理解し、効果的に活用することが重要です。ターゲットとする顧客層がどのような印象を抱くかを考慮し、キーカラー(=主軸となる色)、メインカラー(=全体を支配する主要な色)、アクセントカラー(=部分的に強調する色)を戦略的に選びましょう。配色テクニック(=色の組み合わせ方)としては、類似色(=色相環で隣同士の色)を組み合わせることで調和の取れた印象に、補色(=反対の色)を組み合わせることでコントラスト(=対比・目立ちやすさ)を強調し、目を引くデザインにすることができます。具体的な例として、信頼感を重視する金融機関のサイトでは青系の色が多用され、若者向けのファッションブランドでは、トレンドを反映した鮮やかな色がアクセントとして使われることが多いです。色の組み合わせは、ウェブサイト全体のトーン&マナー(=全体の雰囲気・統一感)を決定づけるため、慎重に検討する必要があります。
◆フォント
フォント(=文字の形・書体)は、ウェブサイトの可読性(=どれだけ読みやすいか)に大きく影響するだけでなく、デザイン全体の印象やブランドの個性を伝える上でも重要な役割を果たします。フォントには大きく分けて、セリフ体(=文字の端に「うろこ」と呼ばれる飾りがある書体、例: Times New Roman)とサンセリフ体(=「うろこ」がないシンプルな書体、例: Arial, Helvetica)があります。セリフ体は伝統的で信頼感のある印象を与えやすく、長文の読解に適しているとされる一方、サンセリフ体はモダンでクリーンな印象を与え、見出しや短いテキストに適しているとされます。ウェブサイトでは、一般的にサンセリフ体が画面表示での可読性が高いとされていますが、デザインの目的やターゲット層に応じて使い分けることが大切です。フォントを選ぶ際は、まずそのフォントが持つ雰囲気(例: フォーマル、カジュアル、エレガント、力強い)を考慮し、ウェブサイトのコンセプトに合っているかを確認します。次に、文字の太さ(=ウェイト)や文字間(=カーニング)、行間(=リーディング)といった要素を調整し、読みやすいように最適化します。複数のフォントを組み合わせる場合は、最大でも2種類程度に絞り、見出し用と本文用で役割を分けるのが一般的です。例えば、見出しには個性的で目を引くフォントを使い、本文にはシンプルで可読性の高いフォントを使うといった具合です。フォントの選択と設定は、ユーザーがコンテンツに集中できるかどうかに直結するため、細部にまで注意を払う必要があります。
◆レイアウト
ウェブサイトのレイアウトとは、テキスト、画像、ボタンなどの要素を画面上にどのように配置するかという設計図のことです。優れたレイアウトは、情報が整理され、ユーザーが目的の情報に迷うことなくスムーズにたどり着けるように導きます。レイアウトの基本原則として、まず「グリッドシステム(=見えない格子線に沿って整列させる方法)」が挙げられます。これは、画面を縦横に分割した格子(グリッド)の上に要素を配置していく手法で、要素の位置が揃い、全体的に整然とした印象を与えることができます。まるで、方眼紙の上に図形を配置するようなイメージです。次に重要なのが「余白(=ホワイトスペース)」です。要素と要素の間に適切な余白を設けることで、それぞれの要素が際立ち、視覚的なノイズが軽減され、コンテンツがすっきりと見やすくなります。余白は、要素を詰め込みすぎないようにするための重要な「間」の役割を果たします。さらに、「視線誘導(=見てもらいたい順番を意識した配置)」もレイアウトの肝です。ユーザーの視線が自然に流れるように、重要な情報やアクションを促す要素(CTAボタン=行動を促すボタンなど)を、視線の動きの法則(例: Zの法則、Fの法則)に沿って配置します。例えば、多くのユーザーは画面の左上から右下へ、またはアルファベットのZやFの形に沿って視線を動かす傾向があるため、これらを意識してコンテンツを配置します。これらの原則を理解し適用することで、ユーザーは情報を効率的に理解し、ウェブサイトを快適に利用できるようになります。
◆画像
ウェブサイトにおける画像は、単なる装飾にとどまらず、情報の伝達、ブランドイメージの向上、ユーザーの感情への訴求など、多岐にわたる重要な役割を担います。適切な画像を選ぶことは、ウェブサイトの印象を劇的に変える力があります。まず、画像の選定においては、ウェブサイトのテーマやブランドイメージと一貫性があるか、そして伝えたいメッセージを効果的に補強できるかどうかが重要です。高解像度(=きめ細かく鮮明な)でプロフェッショナルな印象を与える写真や、コンセプトを象徴するイラストなどを活用することで、ユーザーの興味を引きつけ、信頼感を醸成(=自然に生み出す)することができます。また、画像のファイルサイズはウェブサイトの表示速度に直結するため、画質を保ちつつファイルサイズを最適化する加工(=圧縮処理)が不可欠です。一般的に、JPEG形式は写真に適しており、PNG形式は透過処理(=背景が透明になる加工)が必要な画像やロゴに適しています。さらに、画像の使用にあたっては「著作権(=作品を作った人の権利)」の問題に十分注意が必要です。インターネット上で見つけた画像を無断で使用することは著作権侵害にあたるため、必ず自分で撮影・作成した画像、または著作権フリー素材サイト(=自由に使える素材サイト・利用規約を確認の上)、有料ストックフォトサービスなどを利用しましょう。これらの点に留意し、戦略的に画像をウェブサイトに組み込むことで、より魅力的で効果的なデザインを実現することができます。
「ターゲットに響くデザインの作り方」に焦点を当て、読者が自社のブランドイメージを向上させ、ターゲットユーザーに好印象を与えるデザインを実現するための具体的な方法を解説します。
※ここでいう「ターゲット」とは、ホームページを見てほしい特定のユーザー層のことです。
ペルソナ設定、ブランドイメージの確立、UI/UXデザインの重要性といった要素を深掘りし、ターゲットニーズにある「自社のホームページの目的に合ったデザインを決めたい」という要望に直接応えます。
※「UI/UX」はそれぞれ「ユーザーインターフェース(見た目や操作性)」と「ユーザーエクスペリエンス(使って得られる体験全体)」を指します。
また、uniqueElementsの「最新のWebデザインのトレンドを分かりやすく解説」もここで触れます。
◆ペルソナ設定
ターゲットユーザーの具体的な人物像(ペルソナ)を設定し、そのペルソナに最適化されたデザインを作成するプロセスを解説します。
※「ペルソナ」とは、実際の顧客を想定して作る“理想のユーザー像”のことです(例:30代女性・会社員・スマホで買い物をよくする)。
ペルソナ設定は、デザインの方向性を定める上で不可欠なステップです。ユーザーのデモグラフィック情報(年齢・性別・職業などの属性情報)、行動パターン、ニーズ、課題などを詳細に定義することで、誰のためにデザインしているのかを明確にし、より共感を得られるデザインへと繋げます。
◆ブランドイメージの確立
企業のブランドイメージをデザインに落とし込み、一貫性のある魅力的なウェブサイトを構築する方法を解説します。
※「ブランドイメージ」とは、ユーザーが企業やサービスに対して持つ印象のことです(例:信頼できる・おしゃれ・親しみやすいなど)。
ブランドカラー(企業を象徴する色)、タイポグラフィ(フォントや文字のデザイン)、トーン&マナー(全体の雰囲気や言葉づかいのルール)などを統一することで、訪問者に強いブランド認知を与え、信頼性を高めます。ブランドストーリー(企業の想い・背景)やバリュー(提供価値)を視覚的に表現し、ターゲット顧客の心に響く体験を提供することが重要です。
◆UI/UXデザインの重要性
ユーザーインターフェース(UI)とユーザーエクスペリエンス(UX)の概念を説明し、使いやすく、コンバージョン(=問い合わせや購入などの成果)に繋がりやすいデザインの実現方法を解説します。
UIは見た目の美しさや操作性を、UXはユーザーが製品やサービスを通じて得る体験全体を指します。これらの要素を最適化することで、ユーザーの満足度を高め、ビジネス目標の達成に貢献するデザインを実現します。
ホームページ制作において、魅力的で機能的なウェブサイトを構築するためには、計画的かつ段階的なデザインプロセスが不可欠です。
※「段階的なプロセス」とは、順序を踏んで進める作業の流れ(設計→構成→デザイン)を意味します。
このセクションでは、情報設計から始まり、ワイヤーフレーム、そして最終的なデザインカンプ作成に至るまでの各ステップを、初心者の方にも分かりやすく解説します。
◆情報設計
情報設計は、ホームページ制作の根幹をなす最初のステップです。
※「情報設計」とは、サイト内にどんな情報を置き、どう整理するかを決める作業のことです。
ここでは、ターゲットユーザーがどのような情報を求めているのか、そしてその情報をどのように効率的かつ直感的に提供できるかを考え、ウェブサイト全体の構造(サイトマップ)や各ページのコンテンツ配置を設計します。
ユーザーフロー(ユーザーがサイト内をどの順序で見ていくか)を意識し、迷うことなく目的の情報にたどり着けるような、論理的で分かりやすいナビゲーション設計を目指します。
◆ワイヤーフレーム作成
次に、情報設計で決定した構造とコンテンツ配置を基に、ワイヤーフレームを作成します。
※「ワイヤーフレーム」とは、デザイン前の“白黒の設計図”のようなもので、どこに画像やボタンを配置するかを決める下書きのことです。
色や画像といった装飾要素は含まず、ページの骨格をシンプルに示します。この段階で、要素のサイズや配置バランス、ボタンの位置などを検討し、使いやすさ(ユーザビリティ)に問題がないかを確認します。
◆デザインカンプ作成
ワイヤーフレームで固められたページの骨子に、具体的なビジュアルデザインを加えていきます。
※「デザインカンプ」とは、完成したサイトの見た目を再現した“完成見本”のようなものです。
ここでは、ブランドイメージやターゲット層に合わせて、配色、タイポグラフィ(文字デザイン)、画像、アイコンなどのデザイン要素を決定します。
FigmaやAdobe XDなどのツールを使って作成し、開発前にデザイン全体を確認できるようにします。
ホームページのデザイン制作って、どんなツールを使えばいいか迷いますよね?
たくさんのツールがあって、どれが自分に合っているのか、プロジェクトに最適なのか、判断が難しいものです。
ここでは、ホームページデザイン制作に役立つ主要なツールをいくつかピックアップして、それぞれの特徴やどんな人におすすめかを分かりやすく解説します。
Photoshop
Adobe Photoshopは、写真編集や画像加工の分野で長年プロに愛用されてきた定番ツールです。
※「ラスター形式」とは、画像を小さな点(ピクセル)の集まりとして表現する方式のことです。写真のような画像に向いています。
ホームページデザインでは、バナーやヘッダー画像の作成、写真の修正に使われます。
Illustrator
Adobe Illustratorは、ベクター形式(点と線で描く方式)の編集に特化したツールです。
※拡大・縮小しても画質が劣化しないのが特徴で、ロゴやアイコンなどの作成に最適です。
Figma
Figmaは、ブラウザ上で動作するデザインツールで、複数人で同時編集できるのが強みです。
※「プロトタイピング機能」とは、完成前に動作イメージを確認できる機能のことです。
Canva
Canvaは、テンプレートを使って簡単にデザインを作れるツールです。
※ドラッグ&ドロップ操作で作れるため、デザイン初心者に人気があります。SNS画像やバナー制作に便利です。
ホームページ公開後、デザインが期待通りの効果を発揮しているかを確認し、さらなる改善につなげるための方法を解説します。効果測定(=デザインの成果を数値で確認すること)の指標、ABテストの実施方法、デザインの修正ポイントなどを具体的に説明し、targetNeeds(=読者が求めているニーズ)の「デザインの改善方法を知りたい」という要望に応えます。uniqueElements(=この章で特に扱う特徴的な要素)の「デザインの効果測定に役立つ指標と分析方法を紹介」もここでカバーします。ultimateGoalForTarget(=読者が最終的に目指すゴール)にある「ユーザーにとって使いやすく、コンバージョン(=成果につながる行動)に繋がりやすいホームページのデザインができる」「費用対効果(=かけた費用に対して得られる効果のバランス)の高いデザイン制作を実現できる」といった最終目標達成のために不可欠なプロセスです。
◆効果測定の指標
ホームページのデザイン効果を測るためには、いくつかの代表的な指標(=判断基準)を理解し、分析することが重要です。まず、コンバージョン率(CVR=サイト訪問者のうち、目的の行動を完了した人の割合)は、ウェブサイト訪問者のうち、目標とする行動(商品購入、問い合わせ、資料請求など)を完了した割合を示します。これが高いほど、デザインがユーザーの行動をうまく誘導できていると言えます。次に、直帰率(Bounce Rate=1ページだけ見て離脱した人の割合)は、訪問者がサイトにアクセスした後、他のページを見ずにすぐに離脱してしまった割合です。直帰率が高い場合、コンテンツやデザインがユーザーの期待に応えられていない、あるいはナビゲーション(=メニューや導線)が分かりにくい可能性があります。滞在時間(Time on Site/Page=ユーザーが1ページやサイト全体にどれくらい留まっているか)も重要な指標で、ユーザーがサイトにどれくらいの時間滞在しているかを示します。滞在時間が長いということは、コンテンツに興味を持ち、深くサイトを探索している可能性が高いことを意味します。これらの指標を定期的に確認し、変動があればその原因を分析することで、デザインの課題を発見し、改善につなげることができます。
◆ABテスト
デザインの改善策を検討する上で、ABテスト(=2つのデザインを比較してどちらが良いか検証する方法)は非常に有効な手法です。ABテストとは、ウェブページのデザインやコピーなどの一部を変更した2つのバージョン(AとB)を用意し、どちらのバージョンがより高い成果を上げるかを比較するテストです。例えば、ボタンの色、配置、キャッチコピー、画像などを変更したバージョンを作成し、ランダムにユーザーを振り分けて表示させます。そして、コンバージョン率やクリック率などの主要な指標を計測し、統計的に有意(=偶然ではないと判断できる)な差が見られた方を採用します。ABテストを実施する際は、テストしたい要素を一つに絞り、十分な期間とデータ量を確保することが重要です。これにより、客観的なデータに基づいた意思決定が可能となり、勘や経験に頼るのではなく、ユーザーの実際の行動に即したデザイン改善を進めることができます。
◆デザインの修正
効果測定の結果やABテストの結果が得られたら、それらを基に具体的なデザインの修正・改善を行います。例えば、コンバージョン率が低いページであれば、CTA(Call to Action=ユーザーに行動を促すボタンやリンク)の目立たせ方や、フォームの入力項目の簡略化などを検討します。直帰率が高い場合は、ファーストビュー(=サイトを開いて最初に目に入る部分)でユーザーの関心を引くコンテンツや、明確なナビゲーションの提示が求められるでしょう。ABテストでA案よりもB案のパフォーマンス(=成果の良さ)が優れていると判断された場合は、B案のデザインを正式に採用します。また、これらのデータ分析だけでなく、ユーザーインタビュー(=実際の利用者への聞き取り)やヒートマップ分析(=ユーザーがどこを見て・クリックしているかを可視化するツール)なども併用することで、より多角的にデザインの課題を把握し、ユーザー体験(UX=使いやすさや満足度)を向上させるための修正ポイントを特定できます。継続的な分析と修正サイクル(=定期的な見直しの繰り返し)を回すことが、効果的でコンバージョンに繋がりやすいホームページデザインを実現する鍵となります。
ホームページのデザインは「正解がない」ため、難しく感じるかもしれません。しかし本記事で解説した内容を元に、まずは「このデザインにした理由」を明確にし一歩を踏み出してみましょう。
お読みいただきありがとうございました!
ホームページ制作におけるデザインの決め方

相模原市・町田市・神奈川県央でホームページ制作を検討している皆さん、こんにちは!
「ホームページを作りたいけど、デザインってどうやって決めるの?」「デザインの知識がないから不安…」そう感じているあなたへ。この記事では、ホームページ制作におけるデザインの決め方を、初心者の方にも分かりやすく解説します。デザインの基礎知識から、ターゲットに合わせたデザインの考え方、具体的な制作ステップ、そして成功事例まで。この記事をぜひ参考にしてください。
ホームページのデザインを決める前に考えるべきこと
新規でホームページを制作する必要がある、既存のホームページのデザインをリニューアル(=作り直す・刷新する)したいといった背景を持つ読者に対し、デザイン決定の初期段階で考慮すべき重要な要素を解説します。目的の明確化、ターゲット設定、競合分析(=他社サイトの調査)が、後のデザイン制作を成功させるための土台となることを伝えます。ターゲットニーズ(=お客様が求めていること)にある「自社のホームページの目的に合ったデザインを決めたい」という要望に応えるための導入部分となります。
◆目的を明確にする
ホームページ制作やリニューアルにおける最初のステップは、その目的を明確に定義することです。ホームページが達成すべき具体的な目標は何でしょうか?例えば、新規顧客の獲得(=集客)、ブランドイメージの向上(=会社やお店の印象を良くすること)、製品やサービスに関する情報提供、既存顧客へのサポート、採用活動の強化など、目的は多岐にわたります。目的が明確でなければ、デザインの方向性が定まらず、結果として効果の薄いホームページになってしまう可能性があります。どのような成果を期待するのかを具体的に言語化し、それをデザインに反映させるための羅針盤としましょう。
◆ターゲットを定める
次に、誰にホームページを見てほしいのか、ターゲットとなるユーザー層を具体的に設定することが重要です。ターゲットユーザーを「ペルソナ(=理想的な顧客像)」として具体的に定義することで、彼らのニーズ(=必要としていること)、興味、行動パターン、そして抱える課題を深く理解することができます。例えば、「30代の働く女性で、健康的な食生活に関心がある」といった具体的なペルソナを設定することで、どのような情報を提供すべきか、どのようなトーンで語りかけるべきか、どのようなデザインが好まれるのかといった、デザインやコンテンツ制作における意思決定が格段にしやすくなります。ターゲットに響くデザインこそが、ホームページの成功を左右します。
◆競合サイトを分析する
自社のホームページデザインを検討する上で、競合他社のウェブサイトを分析することは非常に有効な手段です。競合サイトを調査することで、業界のデザイントレンド(=流行の傾向)やユーザーが期待するUI/UX(=使いやすさや見やすさの設計)のレベル感を把握できます。また、競合がどのような情報を発信し、どのような強みをアピールしているのかを理解することで、自社サイトとの差別化ポイント(=他社と違う強み)を見つけ出すヒントが得られます。さらに、競合サイトの良い点や参考になる点は積極的に取り入れ、悪い点や改善すべき点は自社サイトで避けるべき教訓として活かすことができます。この分析を通じて、より魅力的で効果的なデザイン戦略(=狙いを持った計画)を構築しましょう。
デザインの基礎知識
ウェブサイトのデザインは、単に見た目を美しくするだけでなく、ユーザー体験(=使いやすさや心地よさ)やブランドイメージに大きく影響します。このセクションでは、デザインの専門知識がない方でも理解できるように、ホームページデザインの根幹をなす要素を解説します。色彩心理(=色が人の印象や感情に与える影響)、フォントの選び方、レイアウトの基本原則(=配置のルール)、画像の活用法など、具体的な例を交えながら視覚的に分かりやすく説明し、デザインの「なぜ?」を解消していきます。ここでは、デザインにおいて必須となる「色」「フォント」「レイアウト」「画像」の4つの要素を網羅し、専門用語は適宜解説を加えながら、図解やイラストを多用するイメージで、直感的に理解できるような説明を心がけます。
◆色彩
色は、ウェブサイトの第一印象を決定づけ、ユーザーの感情や行動に直接影響を与える強力なツールです。色彩心理学(=色と感情の関係を研究する学問)では、特定の色が人間の心理にどのような影響を与えるかを研究しており、例えば、暖色系の赤やオレンジは活気や情熱、注意を引く効果があり、寒色系の青や緑は落ち着き、信頼感、安心感を与える傾向があります。ウェブサイトのデザインでは、ブランドイメージや伝えたいメッセージに合わせて、これらの色の特性を理解し、効果的に活用することが重要です。ターゲットとする顧客層がどのような印象を抱くかを考慮し、キーカラー(=主軸となる色)、メインカラー(=全体を支配する主要な色)、アクセントカラー(=部分的に強調する色)を戦略的に選びましょう。配色テクニック(=色の組み合わせ方)としては、類似色(=色相環で隣同士の色)を組み合わせることで調和の取れた印象に、補色(=反対の色)を組み合わせることでコントラスト(=対比・目立ちやすさ)を強調し、目を引くデザインにすることができます。具体的な例として、信頼感を重視する金融機関のサイトでは青系の色が多用され、若者向けのファッションブランドでは、トレンドを反映した鮮やかな色がアクセントとして使われることが多いです。色の組み合わせは、ウェブサイト全体のトーン&マナー(=全体の雰囲気・統一感)を決定づけるため、慎重に検討する必要があります。
◆フォント
フォント(=文字の形・書体)は、ウェブサイトの可読性(=どれだけ読みやすいか)に大きく影響するだけでなく、デザイン全体の印象やブランドの個性を伝える上でも重要な役割を果たします。フォントには大きく分けて、セリフ体(=文字の端に「うろこ」と呼ばれる飾りがある書体、例: Times New Roman)とサンセリフ体(=「うろこ」がないシンプルな書体、例: Arial, Helvetica)があります。セリフ体は伝統的で信頼感のある印象を与えやすく、長文の読解に適しているとされる一方、サンセリフ体はモダンでクリーンな印象を与え、見出しや短いテキストに適しているとされます。ウェブサイトでは、一般的にサンセリフ体が画面表示での可読性が高いとされていますが、デザインの目的やターゲット層に応じて使い分けることが大切です。フォントを選ぶ際は、まずそのフォントが持つ雰囲気(例: フォーマル、カジュアル、エレガント、力強い)を考慮し、ウェブサイトのコンセプトに合っているかを確認します。次に、文字の太さ(=ウェイト)や文字間(=カーニング)、行間(=リーディング)といった要素を調整し、読みやすいように最適化します。複数のフォントを組み合わせる場合は、最大でも2種類程度に絞り、見出し用と本文用で役割を分けるのが一般的です。例えば、見出しには個性的で目を引くフォントを使い、本文にはシンプルで可読性の高いフォントを使うといった具合です。フォントの選択と設定は、ユーザーがコンテンツに集中できるかどうかに直結するため、細部にまで注意を払う必要があります。
◆レイアウト
ウェブサイトのレイアウトとは、テキスト、画像、ボタンなどの要素を画面上にどのように配置するかという設計図のことです。優れたレイアウトは、情報が整理され、ユーザーが目的の情報に迷うことなくスムーズにたどり着けるように導きます。レイアウトの基本原則として、まず「グリッドシステム(=見えない格子線に沿って整列させる方法)」が挙げられます。これは、画面を縦横に分割した格子(グリッド)の上に要素を配置していく手法で、要素の位置が揃い、全体的に整然とした印象を与えることができます。まるで、方眼紙の上に図形を配置するようなイメージです。次に重要なのが「余白(=ホワイトスペース)」です。要素と要素の間に適切な余白を設けることで、それぞれの要素が際立ち、視覚的なノイズが軽減され、コンテンツがすっきりと見やすくなります。余白は、要素を詰め込みすぎないようにするための重要な「間」の役割を果たします。さらに、「視線誘導(=見てもらいたい順番を意識した配置)」もレイアウトの肝です。ユーザーの視線が自然に流れるように、重要な情報やアクションを促す要素(CTAボタン=行動を促すボタンなど)を、視線の動きの法則(例: Zの法則、Fの法則)に沿って配置します。例えば、多くのユーザーは画面の左上から右下へ、またはアルファベットのZやFの形に沿って視線を動かす傾向があるため、これらを意識してコンテンツを配置します。これらの原則を理解し適用することで、ユーザーは情報を効率的に理解し、ウェブサイトを快適に利用できるようになります。
◆画像
ウェブサイトにおける画像は、単なる装飾にとどまらず、情報の伝達、ブランドイメージの向上、ユーザーの感情への訴求など、多岐にわたる重要な役割を担います。適切な画像を選ぶことは、ウェブサイトの印象を劇的に変える力があります。まず、画像の選定においては、ウェブサイトのテーマやブランドイメージと一貫性があるか、そして伝えたいメッセージを効果的に補強できるかどうかが重要です。高解像度(=きめ細かく鮮明な)でプロフェッショナルな印象を与える写真や、コンセプトを象徴するイラストなどを活用することで、ユーザーの興味を引きつけ、信頼感を醸成(=自然に生み出す)することができます。また、画像のファイルサイズはウェブサイトの表示速度に直結するため、画質を保ちつつファイルサイズを最適化する加工(=圧縮処理)が不可欠です。一般的に、JPEG形式は写真に適しており、PNG形式は透過処理(=背景が透明になる加工)が必要な画像やロゴに適しています。さらに、画像の使用にあたっては「著作権(=作品を作った人の権利)」の問題に十分注意が必要です。インターネット上で見つけた画像を無断で使用することは著作権侵害にあたるため、必ず自分で撮影・作成した画像、または著作権フリー素材サイト(=自由に使える素材サイト・利用規約を確認の上)、有料ストックフォトサービスなどを利用しましょう。これらの点に留意し、戦略的に画像をウェブサイトに組み込むことで、より魅力的で効果的なデザインを実現することができます。
ターゲットに響くデザインの作り方
「ターゲットに響くデザインの作り方」に焦点を当て、読者が自社のブランドイメージを向上させ、ターゲットユーザーに好印象を与えるデザインを実現するための具体的な方法を解説します。
※ここでいう「ターゲット」とは、ホームページを見てほしい特定のユーザー層のことです。
ペルソナ設定、ブランドイメージの確立、UI/UXデザインの重要性といった要素を深掘りし、ターゲットニーズにある「自社のホームページの目的に合ったデザインを決めたい」という要望に直接応えます。
※「UI/UX」はそれぞれ「ユーザーインターフェース(見た目や操作性)」と「ユーザーエクスペリエンス(使って得られる体験全体)」を指します。
また、uniqueElementsの「最新のWebデザインのトレンドを分かりやすく解説」もここで触れます。
◆ペルソナ設定
ターゲットユーザーの具体的な人物像(ペルソナ)を設定し、そのペルソナに最適化されたデザインを作成するプロセスを解説します。
※「ペルソナ」とは、実際の顧客を想定して作る“理想のユーザー像”のことです(例:30代女性・会社員・スマホで買い物をよくする)。
ペルソナ設定は、デザインの方向性を定める上で不可欠なステップです。ユーザーのデモグラフィック情報(年齢・性別・職業などの属性情報)、行動パターン、ニーズ、課題などを詳細に定義することで、誰のためにデザインしているのかを明確にし、より共感を得られるデザインへと繋げます。
◆ブランドイメージの確立
企業のブランドイメージをデザインに落とし込み、一貫性のある魅力的なウェブサイトを構築する方法を解説します。
※「ブランドイメージ」とは、ユーザーが企業やサービスに対して持つ印象のことです(例:信頼できる・おしゃれ・親しみやすいなど)。
ブランドカラー(企業を象徴する色)、タイポグラフィ(フォントや文字のデザイン)、トーン&マナー(全体の雰囲気や言葉づかいのルール)などを統一することで、訪問者に強いブランド認知を与え、信頼性を高めます。ブランドストーリー(企業の想い・背景)やバリュー(提供価値)を視覚的に表現し、ターゲット顧客の心に響く体験を提供することが重要です。
◆UI/UXデザインの重要性
ユーザーインターフェース(UI)とユーザーエクスペリエンス(UX)の概念を説明し、使いやすく、コンバージョン(=問い合わせや購入などの成果)に繋がりやすいデザインの実現方法を解説します。
UIは見た目の美しさや操作性を、UXはユーザーが製品やサービスを通じて得る体験全体を指します。これらの要素を最適化することで、ユーザーの満足度を高め、ビジネス目標の達成に貢献するデザインを実現します。
デザイン制作のステップ
ホームページ制作において、魅力的で機能的なウェブサイトを構築するためには、計画的かつ段階的なデザインプロセスが不可欠です。
※「段階的なプロセス」とは、順序を踏んで進める作業の流れ(設計→構成→デザイン)を意味します。
このセクションでは、情報設計から始まり、ワイヤーフレーム、そして最終的なデザインカンプ作成に至るまでの各ステップを、初心者の方にも分かりやすく解説します。
◆情報設計
情報設計は、ホームページ制作の根幹をなす最初のステップです。
※「情報設計」とは、サイト内にどんな情報を置き、どう整理するかを決める作業のことです。
ここでは、ターゲットユーザーがどのような情報を求めているのか、そしてその情報をどのように効率的かつ直感的に提供できるかを考え、ウェブサイト全体の構造(サイトマップ)や各ページのコンテンツ配置を設計します。
ユーザーフロー(ユーザーがサイト内をどの順序で見ていくか)を意識し、迷うことなく目的の情報にたどり着けるような、論理的で分かりやすいナビゲーション設計を目指します。
◆ワイヤーフレーム作成
次に、情報設計で決定した構造とコンテンツ配置を基に、ワイヤーフレームを作成します。
※「ワイヤーフレーム」とは、デザイン前の“白黒の設計図”のようなもので、どこに画像やボタンを配置するかを決める下書きのことです。
色や画像といった装飾要素は含まず、ページの骨格をシンプルに示します。この段階で、要素のサイズや配置バランス、ボタンの位置などを検討し、使いやすさ(ユーザビリティ)に問題がないかを確認します。
◆デザインカンプ作成
ワイヤーフレームで固められたページの骨子に、具体的なビジュアルデザインを加えていきます。
※「デザインカンプ」とは、完成したサイトの見た目を再現した“完成見本”のようなものです。
ここでは、ブランドイメージやターゲット層に合わせて、配色、タイポグラフィ(文字デザイン)、画像、アイコンなどのデザイン要素を決定します。
FigmaやAdobe XDなどのツールを使って作成し、開発前にデザイン全体を確認できるようにします。
<< プーズネット制作事例はこちら>>
デザインツールの紹介と選び方
ホームページのデザイン制作って、どんなツールを使えばいいか迷いますよね?
たくさんのツールがあって、どれが自分に合っているのか、プロジェクトに最適なのか、判断が難しいものです。
ここでは、ホームページデザイン制作に役立つ主要なツールをいくつかピックアップして、それぞれの特徴やどんな人におすすめかを分かりやすく解説します。
Photoshop
Adobe Photoshopは、写真編集や画像加工の分野で長年プロに愛用されてきた定番ツールです。
※「ラスター形式」とは、画像を小さな点(ピクセル)の集まりとして表現する方式のことです。写真のような画像に向いています。
ホームページデザインでは、バナーやヘッダー画像の作成、写真の修正に使われます。
Illustrator
Adobe Illustratorは、ベクター形式(点と線で描く方式)の編集に特化したツールです。
※拡大・縮小しても画質が劣化しないのが特徴で、ロゴやアイコンなどの作成に最適です。
Figma
Figmaは、ブラウザ上で動作するデザインツールで、複数人で同時編集できるのが強みです。
※「プロトタイピング機能」とは、完成前に動作イメージを確認できる機能のことです。
Canva
Canvaは、テンプレートを使って簡単にデザインを作れるツールです。
※ドラッグ&ドロップ操作で作れるため、デザイン初心者に人気があります。SNS画像やバナー制作に便利です。
デザインの効果測定と改善
ホームページ公開後、デザインが期待通りの効果を発揮しているかを確認し、さらなる改善につなげるための方法を解説します。効果測定(=デザインの成果を数値で確認すること)の指標、ABテストの実施方法、デザインの修正ポイントなどを具体的に説明し、targetNeeds(=読者が求めているニーズ)の「デザインの改善方法を知りたい」という要望に応えます。uniqueElements(=この章で特に扱う特徴的な要素)の「デザインの効果測定に役立つ指標と分析方法を紹介」もここでカバーします。ultimateGoalForTarget(=読者が最終的に目指すゴール)にある「ユーザーにとって使いやすく、コンバージョン(=成果につながる行動)に繋がりやすいホームページのデザインができる」「費用対効果(=かけた費用に対して得られる効果のバランス)の高いデザイン制作を実現できる」といった最終目標達成のために不可欠なプロセスです。
◆効果測定の指標
ホームページのデザイン効果を測るためには、いくつかの代表的な指標(=判断基準)を理解し、分析することが重要です。まず、コンバージョン率(CVR=サイト訪問者のうち、目的の行動を完了した人の割合)は、ウェブサイト訪問者のうち、目標とする行動(商品購入、問い合わせ、資料請求など)を完了した割合を示します。これが高いほど、デザインがユーザーの行動をうまく誘導できていると言えます。次に、直帰率(Bounce Rate=1ページだけ見て離脱した人の割合)は、訪問者がサイトにアクセスした後、他のページを見ずにすぐに離脱してしまった割合です。直帰率が高い場合、コンテンツやデザインがユーザーの期待に応えられていない、あるいはナビゲーション(=メニューや導線)が分かりにくい可能性があります。滞在時間(Time on Site/Page=ユーザーが1ページやサイト全体にどれくらい留まっているか)も重要な指標で、ユーザーがサイトにどれくらいの時間滞在しているかを示します。滞在時間が長いということは、コンテンツに興味を持ち、深くサイトを探索している可能性が高いことを意味します。これらの指標を定期的に確認し、変動があればその原因を分析することで、デザインの課題を発見し、改善につなげることができます。
◆ABテスト
デザインの改善策を検討する上で、ABテスト(=2つのデザインを比較してどちらが良いか検証する方法)は非常に有効な手法です。ABテストとは、ウェブページのデザインやコピーなどの一部を変更した2つのバージョン(AとB)を用意し、どちらのバージョンがより高い成果を上げるかを比較するテストです。例えば、ボタンの色、配置、キャッチコピー、画像などを変更したバージョンを作成し、ランダムにユーザーを振り分けて表示させます。そして、コンバージョン率やクリック率などの主要な指標を計測し、統計的に有意(=偶然ではないと判断できる)な差が見られた方を採用します。ABテストを実施する際は、テストしたい要素を一つに絞り、十分な期間とデータ量を確保することが重要です。これにより、客観的なデータに基づいた意思決定が可能となり、勘や経験に頼るのではなく、ユーザーの実際の行動に即したデザイン改善を進めることができます。
◆デザインの修正
効果測定の結果やABテストの結果が得られたら、それらを基に具体的なデザインの修正・改善を行います。例えば、コンバージョン率が低いページであれば、CTA(Call to Action=ユーザーに行動を促すボタンやリンク)の目立たせ方や、フォームの入力項目の簡略化などを検討します。直帰率が高い場合は、ファーストビュー(=サイトを開いて最初に目に入る部分)でユーザーの関心を引くコンテンツや、明確なナビゲーションの提示が求められるでしょう。ABテストでA案よりもB案のパフォーマンス(=成果の良さ)が優れていると判断された場合は、B案のデザインを正式に採用します。また、これらのデータ分析だけでなく、ユーザーインタビュー(=実際の利用者への聞き取り)やヒートマップ分析(=ユーザーがどこを見て・クリックしているかを可視化するツール)なども併用することで、より多角的にデザインの課題を把握し、ユーザー体験(UX=使いやすさや満足度)を向上させるための修正ポイントを特定できます。継続的な分析と修正サイクル(=定期的な見直しの繰り返し)を回すことが、効果的でコンバージョンに繋がりやすいホームページデザインを実現する鍵となります。
まとめ
ホームページのデザインは「正解がない」ため、難しく感じるかもしれません。しかし本記事で解説した内容を元に、まずは「このデザインにした理由」を明確にし一歩を踏み出してみましょう。
お読みいただきありがとうございました!