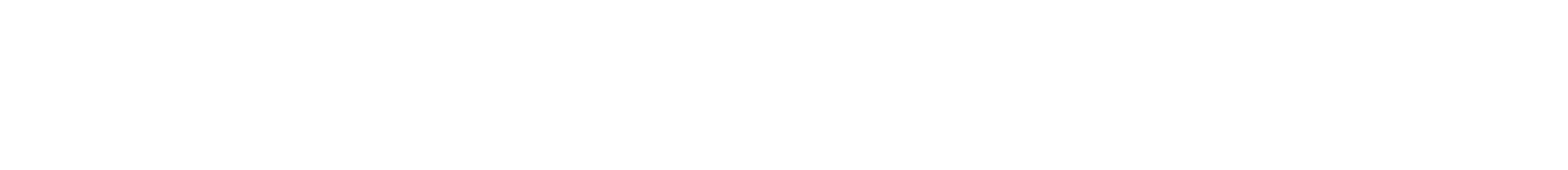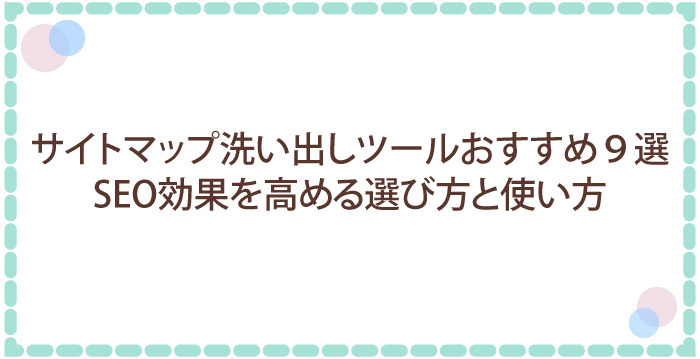
サイトマップ洗い出しツールおすすめ9選|SEO効果を高める選び方と使い方

節目の創立25周年 2026年を迎えて

Googleアナリティクス初心者向けデータ読み取り方マニュアル

HTTPとは?HTTPSとの違いを徹底解説

年末のご挨拶

ドキュランドへようこそ。「衛生兵キューバとアラスカ ウクライナ・夢も人生も諦めない」を見て
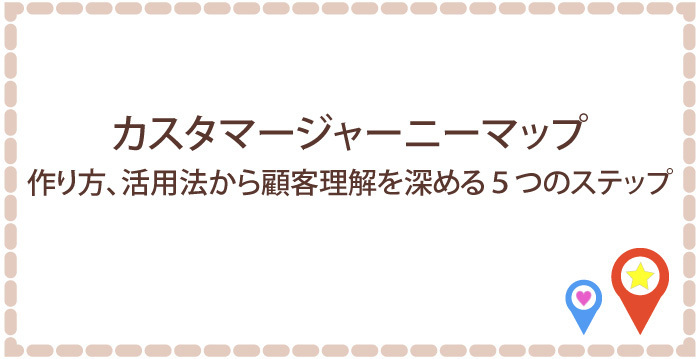
カスタマージャーニーマップの作り方と活用法 顧客理解を深める5つのステップ

アイデア創出力アップ!ブレインストーミングとマインドマップの最強タッグ活用術

SNSフォロワー数激増ガイド!プラットフォーム別攻略法

リッチリザルトで検索順位UP!構造化データ入門

構造化データで検索順位UP!SEO効果と実装方法を分かりやすく解説
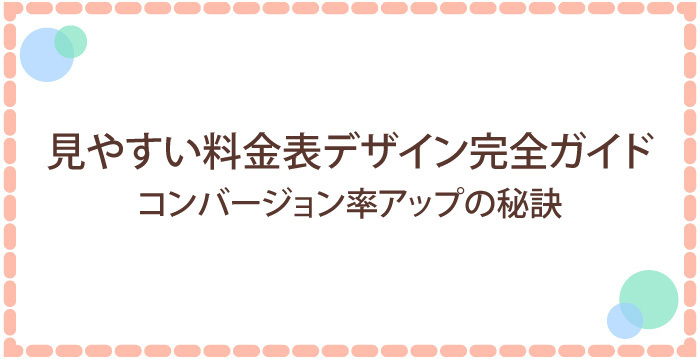
見やすい料金表デザイン完全ガイド コンバージョン率アップの秘訣