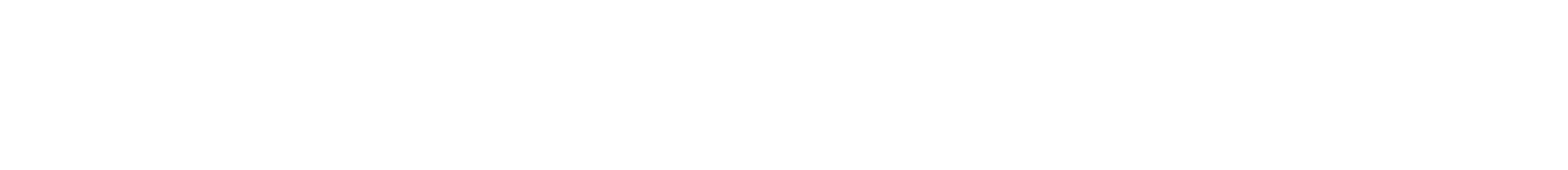日本における地域で活躍するAI事例

AIが支える、地方の「移動の自由」
交通の課題に立ち向かう、新しい選択肢
地方のまちを歩いてみると、かつては通っていたバスが走っていなかったり、バス停が草に埋もれていたりする光景に出会うことがあります。
住民はそこに確かに暮らしているのに、移動手段が失われてしまった地域は、今や日本中に広がっています。
多くの地方が抱えているのは、「移動したい人がいるのに、交通がない」という深刻な課題です。
特に高齢者や車を持たない家庭にとって、買い物や通院に出かけることすら難しくなっているのが現状です。
どうしてこんなことになったのか
原因は一つではありません。
たとえば、地域のバスが「誰も乗っていないのに、決まった時間に走る」という運行を続けてきた結果、採算が取れず減便され、やがて廃止に追い込まれることがあります。
また、運転手の高齢化や人手不足も深刻です。走らせたくても人がいない。そんなジレンマを抱えている自治体も多くあります。
そしてもう一つの問題は、住民のニーズと交通のかたちが合っていないことです。
朝夕だけ通学用にバスを使いたい人、昼間に病院へ行きたい人、週末だけ買い物に出かけたい人。
みんなバラバラな時間に、バラバラな目的地へ行きたいのに、従来の「時刻表」と「固定ルート」では応えきれないのです。
その課題に、AIが入ってきた
そんな状況を打開するために、最近注目されているのが「AIオンデマンド交通」です。
これは、利用者がスマホや電話で乗りたい時間や場所を予約すると、AIがそれらをもとに最適なルートを判断し、効率よくバスを走らせるという仕組みです。
特にユニークなのは、「仮想バス停」の考え方。
実際のバス停ではなく、自宅近くや指定場所を一時的な乗降地点としてAIが設定してくれるため、高齢者でも歩く距離が短くて済みます。
乗る人がいるときだけバスが動く。しかも、複数の利用者をうまく組み合わせて、無駄なく走る。
それが、AIによるオンデマンド交通の大きな特徴です。
実際にどうだったのか
全国ではすでに30以上の自治体がこの仕組みを導入し、実証・運用が進められています。
ある自治体では、導入前のバスは1便あたり0.5人しか乗らない状態だったのが、AI運行に切り替えてからは利用者数が明確に増えました。
また、住民アンケートでは「自宅近くまで来てくれるのがありがたい」「病院に行くのが楽になった」といった声が多く寄せられました。
運営側にとっても、空気を運ぶだけだった運行が減り、ドライバーの拘束時間も短くなります。
さらに、利用データがすべて記録されるので、次の路線改善や政策判断にも役立ちます。
交通というより、生活の話
AIオンデマンド交通は、ただ新しい技術を入れたというだけの話ではありません。
それは、移動の自由を失いかけていた地域に「また動ける」という感覚を取り戻すものです。
大きな駅もなく、コンビニも遠く、車も手放した。そんな場所で暮らしている人にとって、AIがつないでくれる一台のバスは、“生活の一部”なのです。
そして、この仕組みは、特別な地域だけの話ではありません。
どのまちにも、同じような課題があり、同じような人たちが暮らしています。
これからの公共交通にとって大事なのは、「すべての人にとってちょうどよい距離感」をどう作れるか。
そのためにAIができることは、確実に広がり始めています。
出典・参考リンク
- TMJ:高萩市「MyRide のるる」事例
- 国土交通省 東北運輸局:オンデマンド交通の導入状況
- 西日本鉄道(のるーと)運行地域一覧
- AIオンデマンド交通導入地域データ
- メタバース総研:地方自治体におけるAI活用事例